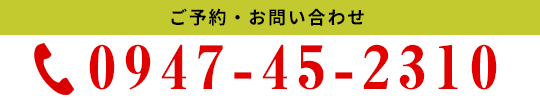英彦山は神様の山(後編)
さて今回は英彦山後編です⛰️
前回の前編をご覧になっていない方は
お読みになってからの方がより理解できるかと思います。
⭐️英彦山は神様の山(前編)
https://doi-shinkyu.com/?p=8891
大雪の中、英彦山の北岳から上宮に行って
写真を撮りながら下山したのが午後3時でした。
偶然にもその日は年に2回開催されるという
高住神社⛩️の護摩だきが終わった直後でした。
遠方から参拝客や僧侶の人たちなど沢山の人で賑やかでした。
その中でお札を販売していた1人のおじさんと
今年の冬だけで5回英彦山に登ったことなど立ち話をしていると、
面白い話を聞かせてあげようと言ってきました。
初め私も軽い気持ちで聞いてたのですが、
英彦山の歴史や神様のことまで初めて聞く内容ばかりで
目から鱗が100枚は落ちました💦
英彦山は霊山で古くから神の山として信仰されてきました。
昔から西日本一の修験の山だったそうで全盛期は門徒さんが8万いたそうです。
山伏の僧帽も最盛期には僧坊3800を数え,その信仰は九州一円に及び,
大峰山,羽黒山と並んで日本の三大修験道場とされていました。
ちなみに今の玉屋神社のところが第一坊だったそうです。
恐らく人の往来も今とは比べ物にならない程だったでしょう。
- XTU S6
英彦山の漢字も大昔は違っていて日(火)子山という表記だったそうです。
これには大きな意味があって英彦山に祀られてる神様に由来します。
日本の最高神は太陽の神様、天照大神(あまてらすおおみかみ)ですよね。
日子山(ひこさん)の主祭神は天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)です。
天忍穂耳命は太陽神である天照大神(あまてらすおおみかみ)の御子で、
稲穂の神、農業神として知られており英彦山神宮の御祭神も天忍穂耳命です。
嵯峨天皇のときに彦山と変わって、1729年(享保14)霊元上皇の
院宣によって英彦山と書くようになったようです。英は称号です
日本は昔から神仏合同で信仰されていました。
英彦山も同様に神仏合同でキリスト教まで受け入れていたようです。
とてつもなく寛大な神様だったようですね💦
それが明治の神仏分離令が出された際に僧房など全て壊されて
その後は実質的に修験の山では無くなってしまいました。
英彦山神宮と高住神社も大昔はもう少し山の上部に
隣り合って建てられていたのが場所を離されたらしいです。
実はその後もっととんでもない話があるのですが、
思いのほか長くなったので次回にお話します☆